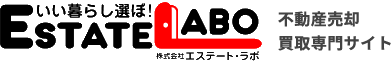【岡崎市】空き家を放置するリスクとは?活用・対策・管理の注意点とデメリットを徹底解説
2025/09/04
岡崎市内に空き家を所有しているものの、「何から手をつければいいかわからない」「遠方に住んでいて管理が難しい」といった悩みを抱えていませんか? 固定資産税を払い続けるだけの空き家は、経済的な負担だけでなく、放置することで思わぬ大きなリスクを生む可能性があります。
この記事では、空き家の活用や管理を検討する上で、つい見落としがちな「注意点」と「デメリット」に焦点を当てて詳しく解説します。安易な判断で後悔しないために、まずは空き家を取り巻く厳しい現実と、正しい対策の進め方を理解しましょう。
1. なぜ空き家対策が急務なのか?放置が招く最大のリスク
「とりあえず現状維持で」と考えている方も多いかもしれませんが、空き家を放置することのデメリットは年々大きくなっています。
最大のリスク:「特定空家」指定と固定資産税の増額
最も注意すべきは、行政による「特定空家」または「管理不全空家」への指定です。管理が行き届かず、周辺環境に悪影響を及ぼすと判断された空き家が対象となります。
そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
著しく衛生上有害となるおそれのある状態
適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
これらの状態と判断され、自治体からの改善「勧告」を受けると、土地にかかる固定資産税の住宅用地特例が解除されます。これにより、土地の固定資産税が最大で6倍、都市計画税が最大で3倍に跳ね上がる可能性があります。これは、空き家所有者にとって最も直接的で大きな経済的打撃です。
その他、放置が引き起こす多様なデメリット
資産価値の低下:建物は人が住まないと急速に劣化します。適切な管理を怠れば、いざ活用しようとした時には資産価値が大幅に下落している可能性があります。
倒壊・破損による賠償責任:台風や地震で屋根材が飛散したり、ブロック塀が倒れたりして、近隣の住宅や通行人に被害を与えた場合、所有者として損害賠償責任を問われる可能性があります。
衛生環境の悪化・害虫の発生:雑草の繁茂は害虫の温床となり、不法投棄を誘発するなど、近隣の生活環境を脅かす原因となります。
防犯上のリスク:人の出入りがない空き家は、放火や不法侵入といった犯罪のターゲットになりやすくなります。
これらのリスクを回避するためにも、早期の対策が不可欠です。
2. その活用、本当に大丈夫?空き家活用の落とし穴と注意点
空き家対策として「活用」を考えるのは自然な流れですが、それぞれの方法にメリットだけでなく、見過ごせないデメリットや注意点が存在します。
ケース1:「賃貸」で活用する場合の注意点・デメリット
安定した家賃収入が魅力的に見える賃貸活用ですが、相応の準備とリスクが伴います。
高額な初期投資(リフォーム費用):人が快適に住める状態にするためには、数十万~数百万円規模のリフォームが必要になるケースがほとんどです。特に水回りや内外装の修繕は必須となるでしょう。
入居者トラブルのリスク:家賃滞納、騒音問題、マナー違反など、入居者とのトラブルは精神的な負担が大きく、自主管理では対応が困難な場合があります。
継続的な管理の手間と費用:入居者が決まった後も、設備の故障対応や定期的なメンテナンス、退去時の原状回復など、管理の手間と費用は継続的に発生します。
空室のリスク:必ずしもすぐに入居者が見つかるとは限りません。空室期間中も固定資産税や管理費は発生し続けます。
ケース2:「売却」で処分する場合の注意点・デメリット
所有し続ける負担から解放される売却ですが、希望通りに進まないことも少なくありません。
希望価格で売れない可能性:建物の状態や立地によっては、想定よりも大幅に低い価格でしか売却できない、あるいは買い手が見つからない可能性があります。
解体費用の負担:建物の劣化が激しい場合、「更地」での売却を求められることがあります。木造家屋でも100万円以上の解体費用がかかるのが一般的です。
契約不適合責任:売却後に、契約書に記載のない建物の欠陥(雨漏り、シロアリ被害など)が見つかった場合、買主から修繕費用や契約解除を求められる可能性があります。
各種費用と税金の発生:仲介手数料や登記費用に加え、売却によって利益が出た場合は譲渡所得税がかかります。
ケース3:「解体」して更地にする場合の注意点・デメリット
管理の手間をなくすために解体を考える方もいますが、これは慎重な判断が必要です。
高額な解体費用:前述の通り、建物の構造や規模によっては数百万円の費用がかかることもあります。
固定資産税の増額:最も注意すべき点です。建物を解体して更地にすると、住宅用地特例が適用されなくなり、土地の固定資産税が大幅に(最大6倍に)上がってしまいます。
活用の見込みがないと塩漬けに:解体したものの、売却もできず、駐車場など他の活用方法も見つからない場合、高い固定資産税を払い続けるだけの「負の資産」になりかねません。
3. 空き家管理の現実。自主管理と委託のメリット・デメリット
活用や処分がすぐに決まらない場合、当面は「管理」を続ける必要があります。管理方法も慎重に選びましょう。
自主管理のメリット・デメリット
メリットは、管理会社に支払う費用を抑えられる点です。
デメリットは、想像以上の手間と時間がかかる点です。
定期的な訪問:最低でも月1回は現地を訪れ、窓を開けての換気、水道管の錆を防ぐための通水、郵便物の確認、庭の草むしりや清掃などが必要です。
遠方の場合の負担:岡崎市から離れた場所にお住まいの場合、交通費や移動時間の負担は計り知れません。
緊急時への対応の遅れ:台風による破損や近隣からのクレームなど、緊急時に迅速な対応が難しいという大きなリスクがあります。
管理委託のメリット・デメリット
メリットは、管理の手間から解放され、専門的な視点で適切に物件を維持してもらえる点です。
デメリットは、当然ながら費用が発生する点です。
管理委託費用:基本的な巡回や報告サービスで、月額5,000円~10,000円程度が相場です。草刈りや簡単な修繕は別途オプション料金となることが一般的です。
サービス内容の確認:どこまでの業務を、どのくらいの頻度で行ってくれるのか、契約前にサービス内容を詳細に確認し、複数の業者を比較検討することが重要です。
4. 行動する前に知っておきたい!岡崎市の制度と相談窓口
自分一人で悩まず、まずは専門家や行政の窓口に相談することが、空き家問題解決の第一歩です。岡崎市では、空き家に関する様々な支援制度や相談窓口を設けています。
岡崎市の補助金制度(一例)
空き家の除却に関する補助制度:管理不全な状態の危険な空き家などを解体する際に、費用の一部を補助する制度があります。条件により補助額の上限が異なりますので、解体を検討する際は必ず事前に市へ相談しましょう。
空き家の改修に関する補助制度:中山間地域での活用や、地域の交流拠点として活用する場合の改修工事費用を補助する制度があります。
※補助制度には予算や期間、詳細な条件があります。利用を検討する場合は、必ず岡崎市の公式ホームページで最新の情報を確認するか、担当部署にお問い合わせください。
公的な相談窓口
空き家のことでどこに相談すればよいか分からない場合は、まずはこちらに連絡してみましょう。
岡崎市役所 住環境政策課 空家対策係
電話番号:0564-23-6024
空き家に関する全般的な相談に応じてくれます。
まとめ:先延ばしにせず、まずは専門家への相談から
空き家問題は、時間が経てば経つほど建物の劣化が進み、対策の選択肢が狭まってしまいます。そして何より、固定資産税の増額という大きなリスクが迫ってきます。
大切なのは、現状を正確に把握し、様々な選択肢のメリットだけでなくデメリットやリスクを十分に理解した上で、ご自身の状況に最も適した対策を決定することです。
「賃貸」「売却」「管理」「解体」――どの道を選ぶにしても、専門的な知識は不可欠です。この記事を参考に、まずは岡崎市の相談窓口や、信頼できる専門家に相談することから始めてみてはいかがでしょうか。早期の行動が、あなたの大切な資産を守ることに繋がります。
〇お問い合わせ方法
* TEL: [0564-57-1333]
* URL: [https://estate-labo.co.jp/]
* お問い合わせフォーム: [https://estate-labo.co.jp/contact/]
* 来店予約: [https://www.estate-labo.com/reservation/select/]
[会社名]株式会社エステート・ラボ
[所在地]岡崎市上地6丁目1-19 明友ビル 101