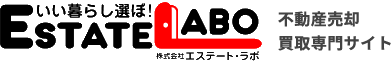離婚後、今の家に住み続ける3つの方法と注意点|後悔しない財産分与とは?
2025/08/16
離婚を決意したとき、多くの人が頭を悩ませるのが「家の問題」です。特に、お子さんの学校や友人関係、あるいは慣れ親しんだ生活環境を考えると、「離婚後も今の家に住み続けたい」と願うのは自然なことでしょう。
しかし、その希望を叶えるためには、住宅ローンや財産分与といった複雑な問題をクリアしなければなりません。感情的な勢いで決断してしまうと、後々「こんなはずではなかった」と後悔するケースも少なくないのです。
この記事では、離婚後も今の家(自宅)に住み続けるための具体的な「3つの方法」と、それぞれに伴う「注意点」を専門家の視点で詳しく解説します。
この記事を読むことで、ご自身にとって最適な選択は何か、そして将来のリスクを回避し、後悔しないための財産分与の方法が分かります。
離婚後に今の家に住み続けるための3つの方法
離婚後、夫婦の共有財産である家にどちらかが住み続ける場合、主に以下の3つの方法が考えられます。それぞれのメリットとデメリットを理解し、ご自身の状況に最も合った方法を選択することが重要です。
方法1:自分が家の所有権を取得する
最もシンプルで、後々のトラブルが少ないのがこの方法です。家の所有権を完全に自分のものにすることで、元配偶者の意向に左右されることなく、安心して住み続けることができます。
メリット
完全に自分の資産となるため、将来的に売却やリフォーム、相続などを自由に行える。
元配偶者との関係が断ち切れるため、精神的な負担が少ない。
住宅ローンを完済すれば、資産として残る。
注意点・デメリット
財産分与の問題: 家の価値から住宅ローン残債を差し引いた金額(アンダーローンの場合)の半分を、代償金として元配偶者に現金で支払う必要があります。
住宅ローンの名義変更: 住宅ローンの名義人が元配偶者の場合、金融機関の審査を経て、ご自身の名義に変更する必要があります。ご自身の収入が審査基準を満たさない場合、名義変更は非常に困難です。
諸経費の負担: 不動産取得税や登録免許税といった登記費用、そして毎年の固定資産税は全てご自身で負担することになります。
【ポイント】代償金の支払いが難しい場合 代償金としてまとまった現金を用意できない場合は、預貯金や保険など他の財産で調整するか、分割払いの交渉をする必要があります。その際は、必ず公正証書を作成し、支払い条件を法的に有効な形で残しておきましょう。
方法2:元配偶者から家を借りる(賃貸借契約)
家の所有者は元配偶者のままで、ご自身が賃借人として家賃を支払い、住み続ける方法です。一般的な賃貸物件と同じように、賃貸借契約を結びます。
メリット
所有権を取得するための代償金や諸経費が不要。
ローン名義変更の必要がなく、ご自身の収入に不安がある場合でも住み続けることが可能。
一定期間だけ住みたい(子どもが卒業するまでなど)場合に適している。
注意点・デメリット
家賃発生と滞納リスク: 当然ながら、毎月家賃を支払う義務が生じます。
元配偶者の都合による退去リスク: 元配偶者が家を売却したくなったり、ローンを滞納して家が競売にかけられたりした場合、退去を求められる可能性があります。
関係が継続することによるストレス: 家の修繕が必要になった際の費用負担の交渉など、離婚後も元配偶者と連絡を取り合う必要があり、精神的なストレスを感じることがあります。
方法3:元配-偶者が所有者として、無償で住まわせてもらう(使用貸借契約)
養育費の代わりなどの理由で、元配偶者の好意により家賃を支払わずに無償で住まわせてもらう方法です。法的には「使用貸借」という契約形態になります。
メリット
家賃の負担がなく、経済的なメリットが非常に大きい。
注意点・デメリット
法的な立場が非常に弱い: 使用貸借は、貸主(元配偶者)の都合でいつでも契約を解除できるのが原則です。元配偶者が再婚したり、心変わりしたりすれば、すぐに退去を求められるリスクがあります。
贈与税の可能性: 無償で住むという経済的利益に対して、贈与税が課される可能性があります(ただし、扶養義務の範囲内と認められれば課税されないケースもあります)。
トラブルの温床: 固定資産税や修繕費の負担をどちらがするのか、明確な取り決めがないと必ずと言っていいほどトラブルになります。口約束は絶対に避けましょう。
【最重要】家に住み続ける際に後悔しないための注意点
どの方法を選択するにせよ、必ず押さえておきたい共通の注意点があります。特に「お金」と「権利」に関わる問題は、曖昧にしておくと将来の大きなトラブルに発展します。
1.住宅ローンの問題をクリアにする
オーバーローンかアンダーローンか: まず、家の現在の価値(査定額)と住宅ローンの残債を正確に把握しましょう。
アンダーローン(家の価値 > ローン残債): プラスの財産として財産分与の対象になります。
オーバーローン(家の価値 < ローン残債): 家は実質的にマイナスの財産となり、財産分与の対象外です。誰が残りのローンを返済していくのか、という問題になります。
ローン名義と連帯保証人: ローンの名義人が誰か、連帯保証人になっているかを確認は必須です。ご自身が連帯保証人から外れる手続きをしない限り、元配偶者がローンを滞納した場合、金融機関からあなたに請求が来てしまいます。連帯保証人から外れるには、金融機関の厳しい審査が必要です。
2.財産分与の取り決めは「公正証書」に残す
「言った」「言わない」の争いを防ぐため、財産分与に関する合意内容は、必ず書面に残しましょう。特に、金銭の支払い(代償金、養育費、慰謝料など)が関わる場合は、強制執行力を持つ「公正証書」を作成することを強くお勧めします。
公正証書を作成しておけば、万が一元配偶者からの支払いが滞った場合に、裁判を起こすことなく相手の給与や財産を差し押さえることが可能になります。
3.家の「適正な価値」を把握する
財産分与を公平に行う大前提として、家の「現在の価値」を正確に知る必要があります。これは、固定資産税評価額ではなく、実際に市場で売買される「時価」です。必ず複数の不動産会社に査定を依頼し、適正な査定額を把握しましょう。
住み続けるリスクを回避する「安全な売却」という選択肢
ここまで「住み続ける」方法を解説してきましたが、ご覧いただいた通り、どの方法にも複雑な問題や将来的なリスクが伴います。
もし、少しでも不安を感じるのであれば、家を「売却」して現金化し、そのお金を夫婦で公平に分けるという方法も有力な選択肢です。
売却のメリット
公平な財産分与: 現金で分けるため、最も公平で分かりやすい解決方法です。
住宅ローン問題の解決: 売却代金でローンを完済できれば、将来の返済リスクや連帯保証人の問題から解放されます。
将来のトラブルを根絶: 固定資産税や修繕費の負担、元配偶者との関係継続といった将来のトラブルの種を根本からなくすことができます。
新生活の資金: 分け合った現金を、それぞれが新しい生活をスタートするための資金に充てることができます。
住み続けることに固執した結果、数年後に元配偶者のローン滞納で家を失い、ご自身も自己破産寸前に…というケースは決して珍しくありません。
まとめ:後悔しない選択のために、まずは専門家へ相談を
離婚という大きな決断の中で、住み慣れた家に関する問題を冷静に判断するのは非常に難しいことです。しかし、感情だけで進めてしまうと、後々取り返しのつかない事態になりかねません。
離婚後に今の家に住み続けたいと考えるのであれば、
家の価値とローン残債を正確に把握する(不動産査定)
3つの方法のメリット・デメリットを理解し、自分に可能か検討する
住宅ローン、税金、将来の費用負担など、お金の問題を全て洗い出す
この3つのステップを必ず踏んでください。
そして、少しでも不安があれば、弁護士や司法書士、不動産会社といった専門家に相談することが、後悔しないための最も確実な方法です。客観的なアドバイスをもとに、ご自身とお子様の未来にとって最善の選択をしてください。
〇お問い合わせ方法
* TEL: [0564-57-1333]
* URL: [https://estate-labo.co.jp/]
* お問い合わせフォーム: [https://estate-labo.co.jp/contact/]
* 来店予約: [https://www.estate-labo.com/reservation/select/]
[会社名]株式会社エステート・ラボ
[所在地]岡崎市上地6丁目1-19 明友ビル 101